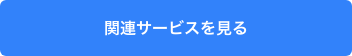新築住宅着工数から見る住宅業界のいまとこれから

現在、新築住宅着工数は減少傾向にあります。これから紹介するさまざまな要因から、今後も減少傾向は続いていくと予想されます。
しかし、新築住宅着工数の減少の要因を把握することで、対策を打つキッカケを知ることができるかもしれません。
また、着工数が減少していくなかでも新たなニーズは生まれています。お客さまが持つ新たなニーズをつかみ、自社の発展につなげるアイデアを創出していきましょう。
今回の記事では、新築住宅着工数から見る住宅業界のいまとこれからの可能性についてご紹介します。
目次[非表示]
- 1.伸び悩む新設住宅着工数
- 1.1.理由1.貸家ブーム
- 1.2.理由2.リーマンショックと同等の不景気
- 1.3.理由3.人口の減少
- 1.3.1.・住宅業界に迫る人口問題
- 1.3.2.・人口が増えている地域もある
- 2.住宅業界に生まれた新たなニーズ
- 3.まとめ
伸び悩む新設住宅着工数
国土交通省が2019年に公表した建築着工統計調査によると、2018年の新築住宅着工数は94万2,370戸、前年から2.9%減少したとあります。特に貸家が5.5%減と大きく落ち込んでいることがわかります。
2016年を見ると着工数は増加しており、2017、2018年の2年連続で減少しただけでは今後の着工数の変化を予想することはできません。
しかし、着工数は次の3つの理由から減少していくと考えられます。
理由1.貸家ブーム
2012年から伸びていた貸家の着工数が、2018年に落ち込みました。その要因のひとつに、2015年に行われた相続税の改正による、貸家ブームが関係すると考えられます。
遺族に残す財産の評価額が一定を超えると相続税が課されますが、2015年の改正に伴い、その一定のラインが引き下げられ、課税対象になる財産を持つ対象者が増加しました。
相続税には、財産を住宅という形で相続する場合、現金よりも評価額を下げてくれるシステムがあります。その節税システムを目的とした貸家へのニーズが高まり、貸家の新築住宅着工数が増加し、貸家ブームが起きました。
この貸家ブームにより、新築住宅が数多く供給されたため、現在は新築住宅着工数を増やしても供給過剰につながる可能性があります。
理由2.リーマンショックと同等の不景気
同じく建築着工統計調査によると、2009年にも着工数が大きく落ち込んでいます。これは前年に起こったリーマンショックによる不景気が要因のひとつであると考えられます。
2020年3月現在、日本では新型コロナウイルスの影響により、リーマンショックと同等かそれ以上に経済が低迷している状況です。リーマンショックでは前年比約-30%の着工数となりました。2020年はそれ以上の減少を覚悟しておく必要があるかもしれません。
理由3.人口の減少
・住宅業界に迫る人口問題
日本の人口の変化と着工数の変化に影響があるといわれています。人口が減少すれば、住宅が供給過多になり着工数は減少していきます。
総務省が2020年3月に公表した人口推計によると、直近10年の日本の人口は減少傾向にあり、2016年の情報通信白書には、少なくとも2060年までは減少傾向であると予想されています。今後、住宅業界にますます向かい風が吹くことになるでしょう。
(参考:総務省 2020年「人口推計 -2020年(令和2年)3月報-」)
・人口が増えている地域もある
その一方で、首都圏の人口は年々増加しています。東京都総務局が2019年に公表した東京都の人口(推計)によると、東京都の人口は約60年前から2018年まで増加傾向にあります。また、東京都のなかでも23区での人口増加が目立ち、都市部へ人口が集中していることがわかります。
(参考:東京都総務局 2019年「東京都の人口(推計)」の概要(平成31年1月1日現在)」)
住宅業界に生まれた新たなニーズ
以上のデータから、住宅業界が厳しい状況にあることは間違いありません。しかし、逆境なりにニーズが生まれ、住宅業界にも打つ手は残されています。ここでは、ニーズの例を2つ紹介します
1.シェアハウス
国土交通省が2014年に行った「シェアハウス等における契約実態等に関する調査」によると、2006年以降参入事業が大幅に増加しているとあります。また、物件所在地は東京都がダントツで多く、入居理由も“立地がよかったから” “家賃が安いから”という理由が多く見られます。
(参考:国土交通省 2014年「シェアハウス等における契約実態等に関する調査」)
これらのことから、安く東京などの都心部に住みたいというニーズが生まれていることがわかります。
2.リモートワーク
世間に広がりをみせる、自宅で働くリモートワーク。もし、リモートワークという働き方が普及していけば、場所を選ばずに仕事ができるようになります。
会社への通勤を基準に住む場所を決めていた人も多いでしょう。東京の会社に勤めていた人にもリモートワークによって地方に住む選択肢が生まれるのです。
リモートワークの普及は住宅業界にとってチャンスといっていいでしょう。
これらはあくまでも一例で、ほかにも住宅へのニーズはたくさんあります。顧客のニーズをつかむためにも、時代の流れを読むことが重要です。
まとめ
今回は新築住宅着工数から見る住宅業界の現状と、住宅業界の可能性について説明しました。
統計が示すとおり、住宅業界が厳しい状況にあるのは認めざるを得ない事実でしょう。着工数は減少傾向にあり、人口の減少に伴って住宅のニーズも減っていくと考えられます。
しかし、時代の変化とともに、新たなニーズが生まれてきます。今後も住宅に求められている役割の変化を見逃さないようにしましょう。