【建築デザインにおける意匠権の基礎知識】権利内容や登録条件、侵害時の判断・対応方法をやさしく解説
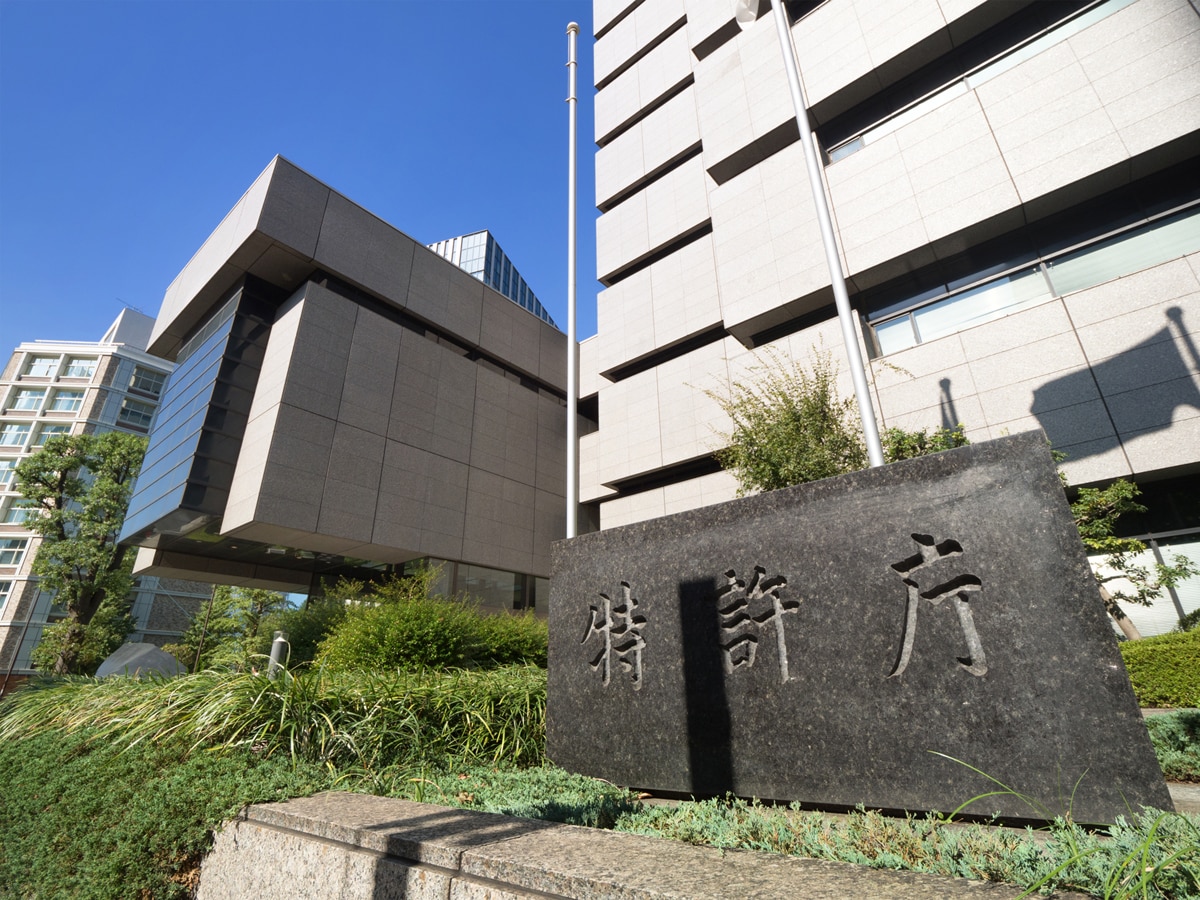
目次[非表示]
- 1.意匠権とは何か?~建築との関係~
- 2.意匠権の登録条件と注意点
- 2.1.①工業上利用できること
- 2.2.②新規性があること
- 2.3.③創作性(創作非容易性)があること
- 3.意匠権侵害の判断基準とは
- 4.意匠権が侵害されたら? 対応方法と防衛策
- 4.1.①法的措置による救済
- 4.2.②権利取得と事前対策による防衛
- 5.執筆者
意匠権とは何か?~建築との関係~
意匠権とは、新しく創作したデザイン(意匠)を独占的に利用できる権利です。日本の意匠法は、新たなデザインの創作を保護・利用することで創作意欲を奨励し、産業の発展に寄与することを目的としています。意匠権は特許庁に意匠を出願して登録することで初めて発生し、登録されたデザインを「登録意匠」といいます。
意匠法では「意匠」を広く定義しており、従来の物品(製品)だけでなく建築物(その部分を含む)の形状・模様・色彩などであって、視覚を通じて美感を起こさせるものが意匠に含まれます。この定義改正により、2020年(令和2年)から建築物の外観や内装のデザインも意匠権で保護できる対象に加わりました。
それ以前は、建築物自体は意匠登録できませんでしたが、改正後は店舗や住宅の外装・内装デザインを模倣された場合に意匠権侵害として差し止めや損害賠償を求めることが可能になりました。
意匠権の登録条件と注意点
意匠権を取得するには、デザインについて特許庁で意匠登録を受ける必要があります。そのために満たすべき主な意匠権登録条件(登録要件)は次のとおりです。
①工業上利用できること
製品や建築物として産業上の利用(量産や反復利用)が可能なデザインであることです。一点ものの純粋な美術作品などは量産できないため対象外と考えられますが、建築物のデザインは実際に建築可能であればこの要件を満たすといえます。
②新規性があること
世界中どこにも同じデザインが存在しない新しい意匠であることです。意匠法第3条第1項では、出願前に公然と知られた意匠や刊行物に記載・公開された意匠、またそれらに類似する意匠は登録できないと定めています。公開済みのありふれたデザインに独占権を与えても産業の発達に寄与しないため、この新規性は最も基本的な条件です。
なお、自身のデザインを先に発表してしまった場合でも、一定の条件下では公表後1年以内なら新規性を失わなかったものとみなす例外規定(意匠法第4条)もあります。しかし原則として公開前に出願するのが望ましいでしょう。
③創作性(創作非容易性)があること
既存のデザインや形状から誰でも容易に思いつくような意匠ではないことも必要です。意匠法第3条第2項は、その意匠の属する分野の通常の知識を持つ者が既知の形状や画像から容易に創作できる意匠は登録できないと規定しています。言い換えれば、ある程度独創的な工夫が凝らされていることが求められるのです。
このほか、他人に先に出願されていないこと(先願主義)も重要です。同じまたは類似のデザインについて先に別の人が出願していれば、後から出した自分の出願は登録を受けられません。また、公序良俗を害するおそれがある意匠(たとえば国旗やわいせつなデザインなど)は登録できないと法律で定められています。
特に建築分野では、設計を宣伝目的で公表したくなることもありますが、意匠権を狙う場合は出願前に公開しすぎないよう注意し、新規性を保ったまま手続きを進めることが肝心です。
意匠法第3条(意匠登録の要件) 一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠 2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 |
(出典:e-GOV法令検索『意匠法』)
意匠権侵害の判断基準とは
無事に意匠登録がされれば、意匠権者はその登録意匠およびそれに類似する意匠を業として無断で実施(製造・販売・建築など)されないよう排他的に支配できます。裏を返せば、第三者が登録意匠と同一もしくは紛らわしいほど似たデザインを許可なく商品化・建築すれば、意匠権の侵害となります。
侵害かどうかの判断はデザインの全体的な見た目(需要者の視覚による美感の印象)に基づいて行われ、細部が多少異なっていても見る人に与える印象が共通するかで類似かどうかが決まります。
つまり、ほんのわずかな変更では逃れられず、登録意匠とほぼ同じ意匠を作ってしまえば侵害リスクが高いということです。
建築デザインにおいても、部分的な違いではなく全体として似ているかが問われます。実際に、ある住宅メーカーが特徴的な住宅外観デザイン(正面の柱と梁で十字を形作る意匠)を部分意匠として登録し、それと類似する外観の住宅を被告会社が建築・販売した事件では、裁判所は両者のデザインは全体的に形状が類似すると判断し、被告会社に対して販売差し止めと約85万円の損害賠償支払いを命じた事案もあります。
このように、建物の外観意匠も法的に保護されており、安易にまねすれば意匠権侵害と認定される可能性があります。
意匠権が侵害されたら? 対応方法と防衛策
意匠権が侵害された場合の対応方法や、侵害を防ぐための防衛策にはどのようなものがあるでしょうか。大きく分けて、次のポイントが挙げられます。
①法的措置による救済
自社の意匠権が侵害された場合、まず侵害者に対し差し止め請求(侵害行為の停止要求)や損害賠償請求といった法的措置を取ることができます。実際に意匠権者は、他人が自分の登録意匠を無断使用した場合にその使用の差し止めや損害賠償を求めることが可能です(意匠法37条、民法709条)。
建築物の場合、既に建てられた建物の除去までは認められないケースもありますが、少なくとも今後の使用・販売等をやめさせ、被った損害の補填を請求できます。もし自社が逆に他社の意匠権を侵害してしまった場合は、速やかにデザインの使用中止や変更を検討し、必要なら専門家(弁護士や弁理士)に相談することが重要です。悪質な意匠権侵害には刑事罰が科される可能性もありますが、まずは差し止め・賠償といった民事上の対応が中心となります。
②権利取得と事前対策による防衛
模倣被害を防ぐには、自社デザインを積極的に意匠登録しておくことが有効です。独創的な建築デザインは早めに意匠出願して権利化しておくことで、類似デザインが他社によって使用された際に差し止め請求など法的措置を取れるようになります。
一方、新しく建物や内装のデザインを手がける際には、他人の意匠権を侵害しないよう事前調査を徹底することも欠かせません。特許庁のデータベース等で既に登録された意匠を調べ、類似デザインを避けることで、知らずに他社の権利を侵してしまうリスクを減らせます。日頃からこうした対策を講じておけば、いざというときに安心です。
建築の世界でもデザインの知的財産としての保護が重要になっています。意匠権の制度を正しく理解し活用することで、自身の創造的な建築デザインを守りつつ、他者の権利トラブルも未然に防ぐことができます。ぜひ意匠権の基礎知識を押さえ、安心してデザイン活動に取り組んでください。
●記事のおさらい
最後に、今回の内容をQ&Aで確認しておきましょう。
Q:建築デザインも意匠権で保護されるのですか?
A:はい。2020年の意匠法改正により、建築物や内装のデザインも意匠権の保護対象となりました。これにより、住宅や店舗などの外観・内装デザインを模倣された場合、法的に差し止め請求や損害賠償請求が可能となっています。
Q:意匠権を取得するにはどうすればよいですか?
A:意匠権を取得するには、特許庁に意匠登録出願を行い、「新規性」「創作性」などの要件を満たす必要があります。出願前にデザインを公開すると新規性を失うおそれがあるため、事前の公開は避けましょう。
●関連コラムはこちら
≫ 【住宅会社向け】会社がネット上で誹謗中傷を受けた際の対応・対策について徹底解説
執筆者
弁護士法人コスモポリタン法律事務所
杉本 拓也(すぎもと たくや)
単なる法的助言を行う法律顧問ではなく、企業内弁護士としての経験を活かして、事業者様により深く関与して課題を解決する「法務コンサルタント」として事業者に寄り添う姿勢で支援しております。国際投融資案件を扱う株式会社国際協力銀行と、メットライフ生命保険株式会社の企業内弁護士の実績があり、企業内部の立場の経験も踏まえた助言を致します。






