【2025年建築基準法改正版】許容応力度計算の詳細とメリット・デメリットを解説
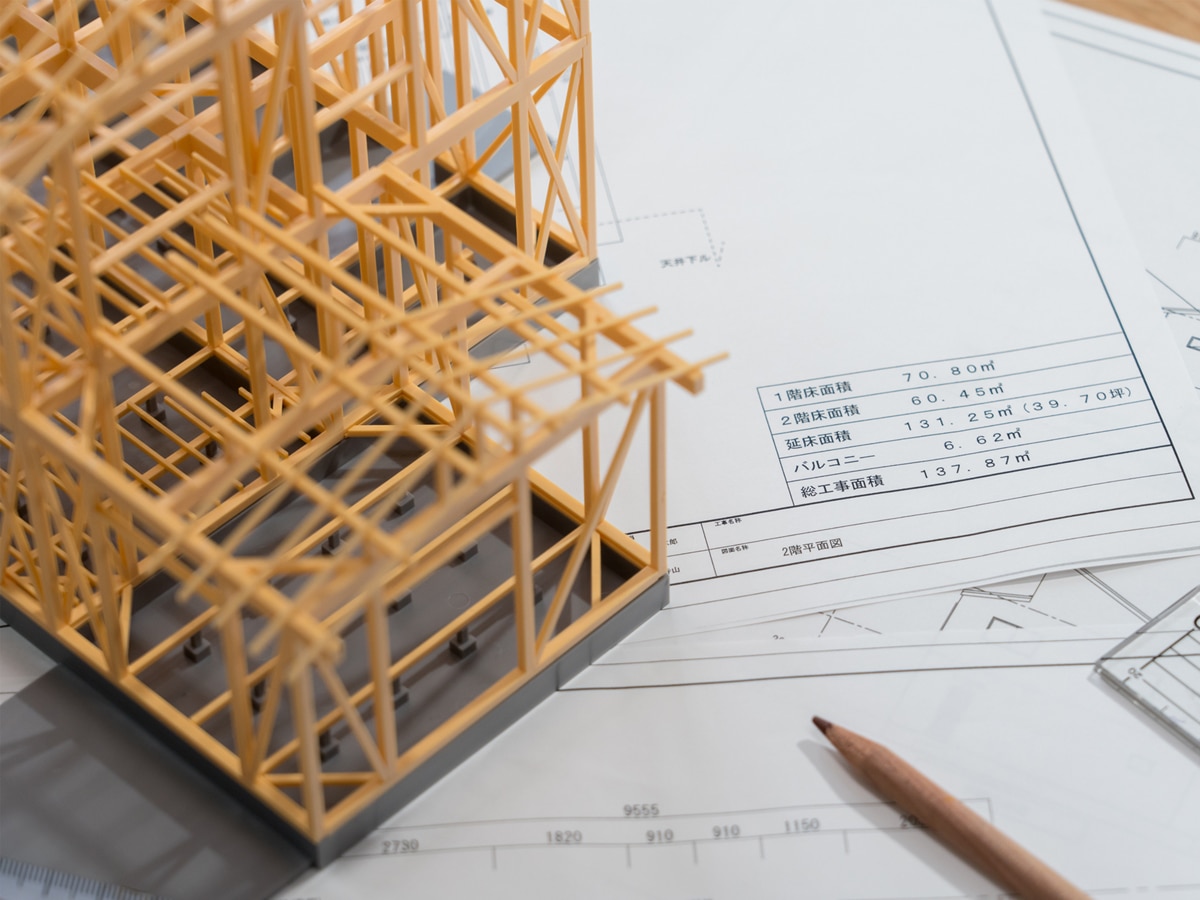
2025年4月の建築基準法改正により、法規の内容が大きく見直されます。そのなかでも注目されているのが、構造計算「許容応力度計算」の一部義務化です。
これまで構造計算が不要とされていた建築物にも適用が広がることで、さまざまな課題や対応が求められるようになります。
制度を知らずにいると、罰則の対象になる可能性もあるため注意が必要です。
この記事では、許容応力度計算の基本から、壁量計算との違い、メリット・デメリット、そして法改正のポイントまで詳しく解説します。
今後の設計や計画に役立てていただければ幸いです。
目次[非表示]
- 1.建構造計算の許容応力度計算とは? 知っておくべき基礎知識
- 2.許容応力度計算のメリットとデメリット
- 2.1.許容応力度計算におけるメリット
- 2.1.1.1.安全性が高い
- 2.1.2.2.意匠設計の自由度が高まる
- 2.2.許容応力度計算におけるデメリット
- 2.2.1.1.計算・設計・変更に時間と費用がかかる
- 2.2.2.2.希望の計画が通らない可能性がある
- 2.2.3.3.既存建築物の価値低下
- 3.2025年法改正に伴う構造計算義務化の概要と注意点を解説
- 3.1.構造計算義務化の目的と対象建築物
- 3.2.法改正に伴い注意すべき2つのポイント
- 3.2.1.1.追加費用の発生
- 3.2.2.2.着工できない可能性
- 4.執筆者
- 4.1.瀧澤 成輝(二級建築士)
建構造計算の許容応力度計算とは? 知っておくべき基礎知識
構造計算とは、建物の安全性を検討、確認するために行われています。建物にはさまざまな荷重が想定されます。たとえば、自重・地震・風圧・積雪などが挙げられます。
構造計算には、以下のとおりいくつかの方法があります。
|
本章では、許容応力度計算の基礎知識について詳しく解説するとともに、多くの方が疑問に感じる「壁量計算と許容応力度計算の違い」についても、分かりやすく解説していきます。
許容応力度計算とは?概要と目的
許容応力度計算とは、構造計算における計算の一つで、建築物の構造部材にかかる応力(力のかかり具合)を算出し、それが許容範囲内に収まるかどうかを確認する計算方法のことを指します。
建物に加わる荷重(自重・積載荷重・風荷重・地震荷重など)を考慮し、各部材の強度が十分であるかを細かく計算します。
この計算により、安全性の高い建築物の設計となり、地震や台風などの外的要因に対して建物が十分に耐えられることが証明されます。
(出典:国土交通省『構造計算適合性判定制度に係る関連データ』)
構造計算の「許容応力度計算」と「壁量計算」の違い
壁量計算は、地震や台風などの横の力に対して倒れないか検証する簡易的な計算方法です。壁の量だけで耐震等級を計算するため、配置やバランスなどは考慮されません。
一方、許容応力度計算は地震や台風などの横の力に加えて建物の自重や積載荷重などの鉛直力が建物にかかる力も考慮し計算します。
さらに、各階の強度や偏心率、部材にかかる力もチェックされます。
壁量計算と許容応力度計算の違いを表にまとめると以下のとおりです。
壁量計算 |
許容応力度計算 |
|
建物の直下率 |
× |
○ |
床面の強度 |
× |
○ |
屋根下地の強度 |
× |
○ |
風の強さ |
× |
○ |
地震の強さ |
× |
○ |
接合部の強度 |
× |
○ |
柱などの部材の強さ |
× |
○ |
壁量計算は無償で対応するところがほとんどですが、許容応力度計算は計算が複雑なため、第三者機関へ依頼することになり、費用が発生する場合があります。
許容応力度計算のメリットとデメリット
建築物の安全性を確保するために、構造計算にはさまざまな手法があります。
そのなかでも「許容応力度計算」は、構造部材にかかる力を詳細に分析し、安全な設計を行うための重要な計算方法です。
一方で、一般的に使用される「壁量計算」は簡易的な計算手法であり、許容応力度計算とは目的や精度が異なります。
本章では、許容応力度計算の概要と目的、壁量計算との違いについて解説します。
許容応力度計算におけるメリット
メリットは主に以下の2つです。
1.安全性が高い 2.意匠設計の自由度が高まる |
1.安全性が高い
許容応力度計算では、前章で解説したとおり風圧などの横の力と自重などの鉛直力などを考慮し計算します。そのため、柱・梁・接合部など個別に評価をすることができます。
さらに、地震や台風などの自然災害に対しても、どの部分にどれだけの負荷がかかるかを正確に把握でき、安全性の高い構造設計ができます。長期にわたって安心して使用できる建物となるでしょう。
2.意匠設計の自由度が高まる
許容応力度計算を用いることで、構造的な柱・梁・接合部などを個別に評価することができるため、どの部分にどれだけの負荷がかかるかを正確に把握できるようになります。
そのため、開放感のある大空間、壁の少ない開口部の多いプラン、吹き抜けや斜め壁といった複雑な形状にも柔軟に対応することが可能となります。
壁量計算では困難だった設計案も、構造の根拠を明確に示すことで実現しやすくなることは間違いありません。デザイン性を重視する住宅や店舗、特殊な用途の建物においては必須となります。
許容応力度計算におけるデメリット
デメリットとしては以下の3つが考えられます。
1.計算・設計・変更に時間と費用がかかる 2.希望の計画が通らない可能性がある 3.既存建築物の価値低下 |
1.計算・設計・変更に時間と費用がかかる
許容応力度計算を行うには、第三者機関を通して行うことになります。そのため、手間や時間そして費用もこれまで以上にかかることが予想されます。
構造計算書はA4用紙で数百枚にも及ぶ大規模なものとなるため、工務店やハウスメーカーにとっては、業務量の増加を避けるのは難しいでしょう。
2.希望の計画が通らない可能性がある
これまでは構造計算を行わなくても建築可能だったために実現できていた建物が、2025年4月の法改正により、構造的な制約から建築主や設計者の希望するデザインやプランが実現できなくなるケースも考えられます。
すべての希望がそのまま実現するとは限りません。
そのため、あらかじめご要望の優先順位を明確にし、「必ず実現したいこと」と「可能であればかなえたいこと」を整理しておくことが大切です。
3.既存建築物の価値低下
法改正により、2025年4月以前に建てられて構造計算されていない建物は「既存不適合建物」となります。
旧基準に基づいて建てられた建物や、簡易な構造計算のみで設計された物件については、耐震性や安全性の面で見劣りすると判断される可能性があり、相対的に市場価値が下がることも考えられます。
構造に関する基本的な知識を身につけておくことで、設計・施工・資産管理における判断がより的確に行えるようになります。
建物構造の種類とその特徴について知りたい方には、以下の記事がおすすめです。
≫ おすすめの記事:【建築業界の基礎知識】建物構造の種類とその特徴について分かりやすく解説
2025年法改正に伴う構造計算義務化の概要と注意点を解説
2025年4月の建築基準法改正により、確認申請に構造計算を添付することが義務化されます。
本章では、2025年4月からの法改正による構造計算義務化の背景と対象となる建物の基準、それに伴う注意すべきポイントについて解説していきます。
構造計算義務化の目的と対象建築物
2025年4月の建築基準法改正と併せての建築物省エネ法の改正により、2025年4月から原則すべての新築住宅に省エネ基準適合が義務付けられるため、4号特例を縮小し、審査対象を統一させるのが目的です。
建築物省エネ法とは? 2022年(令和4年)6月に公布された炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律。 |

(出典:国土交通省『2025年4月から4号特例が変わります』)
対象となるのは、以下の建物です。
|
このため、ほとんどの建物に対して構造計算が必要となります。
法改正に伴い注意すべき2つのポイント
2025年4月の建築基準法改正により、建築業界では以下の2つの重要なポイントに注意が必要です。
1.追加費用の発生 2.着工できない可能性 |
1.追加費用の発生
前章で解説しましたが、2025年4月の建築基準法改正により、従来の「4号特例」が縮小され、多くの木造2階建て住宅等において構造計算書の提出が義務化されます。
これに伴い、設計者や施工者は新たな業務への対応が必要となり、業務量が増加することが予想されます。
たとえば、それまで打ち合わせを進めていた内容が2025年4月をまたいでしまった場合、構造計算にかかる費用や、それに伴う人件費などが追加で発生し、建築主にとって想定外のコスト負担となる可能性があります。
2.着工できない可能性
構造計算の義務化により、確認申請時に必要な図書が増加し、審査に要する時間が延びる可能性があります。
特に、これまで確認申請や構造計算を省略してきた会社は、慣れない手続きへの対応に時間がかかることが考えられます。
その結果、確認申請や構造計算の完了までに予想以上の時間を要し、着工の遅れや工期の延長につながる可能性がありますので注意しましょう。
●記事のおさらい
最後に、今回の内容をQ&Aで確認しておきましょう。
Q:許容応力度計算とは何ですか?
A:建物にかかる荷重(自重・積載荷重・風荷重・地震荷重など)に対し、柱や梁などの部材が安全な範囲で力に耐えられるかを計算する方法のことを指します。
Q:壁量計算と許容応力度計算の違いは何ですか?
A:壁量計算は地震や台風などの横の力に対して倒れないかを検証する簡易的な計算方法で、部材や配置の強度までは考慮しません。一方、許容応力度計算は鉛直力や接合部の強度なども含めたより詳細な構造計算方法です。
Q:許容応力度計算を行うメリットは何ですか?
A:「建物の安全性が高まる」「大空間や吹き抜けなど意匠設計の自由度が向上する」の2点が挙げられます。
Q:許容応力度計算のデメリットは何ですか?
A:主に「計算・設計・変更に時間と費用がかかる」「希望どおりの設計が難しくなる可能性がある」「既存建物の市場価値が下がる可能性がある」という3点が考えられます。
Q:2025年の建築基準法改正では何が義務化されますか?
A:「2階建て以上の建物」または「200m2を超える建物」に対し、省エネ基準への適合と構造計算書の添付が義務化されます。4号特例の適用範囲が大幅に縮小されます。
Q:法改正により注意すべきポイントは?
A:「構造計算対応による追加費用の発生」「確認申請の遅れにより着工できない」といった問題が考えられます。十分に注意しましょう。
●関連コラムはこちら
≫ 【建築業界の基礎知識】建物構造の種類とその特徴について分かりやすく解説
≫ 建築構造におけるヤング係数(弾性係数)について分かりやすく解説
執筆者
瀧澤 成輝(二級建築士)
住宅リフォーム業界で5年以上の経験を持つ建築士。
大手リフォーム会社にて、トイレや浴室、キッチンなどの水回りリフォームを中心に、外壁塗装・耐震・フルリノベーションなど住宅に関する幅広いリフォーム案件を手掛けてきた。施工管理から設計・プランニング、顧客対応まで、1,000件以上のリフォーム案件に携わり、多岐にわたるニーズに対応してきた実績を持つ。
特に、空間の使いやすさとデザイン性を両立させた提案を得意とし、顧客のライフスタイルに合わせた快適な住空間を実現することをモットーとしている。現在は、リフォームに関する知識と経験を活かし、コンサルティングや情報発信を通じて、理想の住まいづくりをサポートしている。






