建設業で無許可営業を行うことの問題や罰則について分かりやすく解説
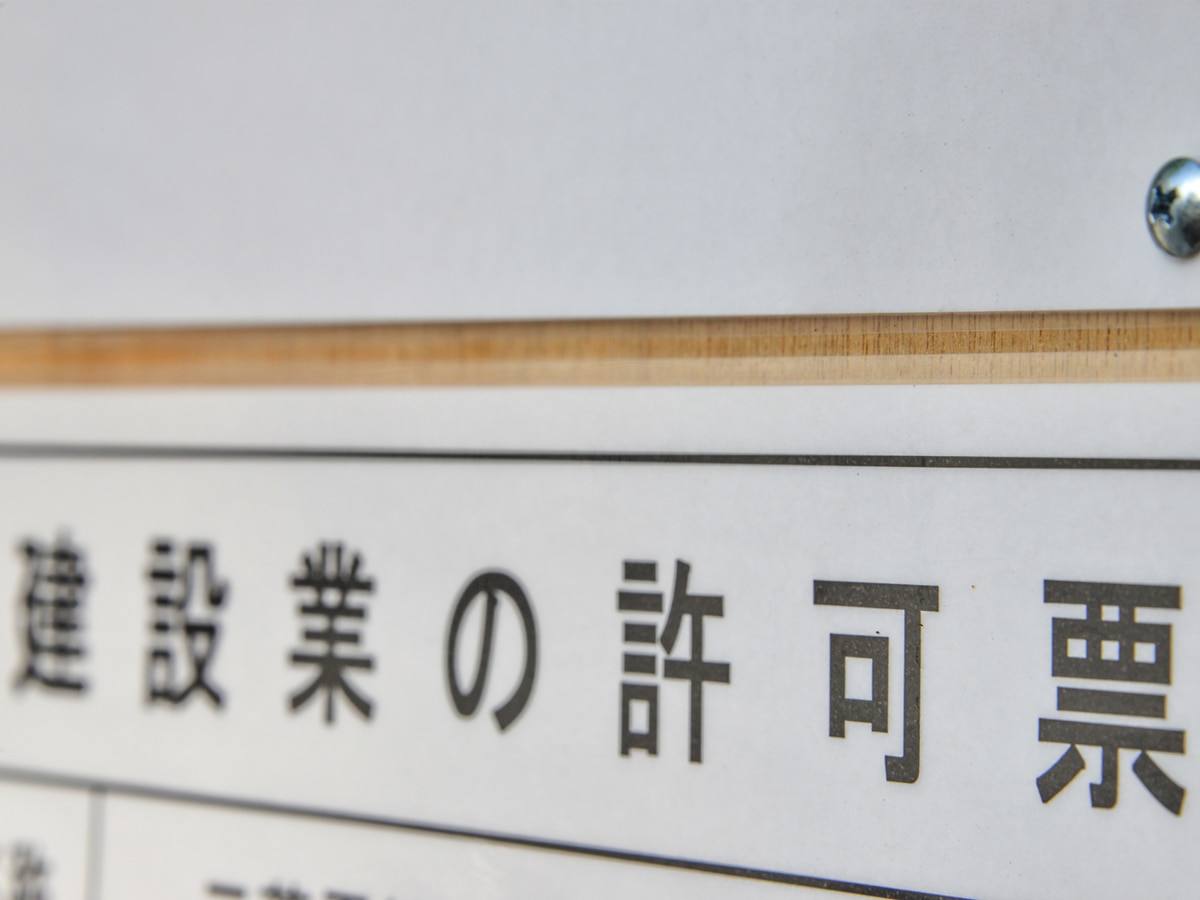
目次[非表示]
建設業許可が必要な工事とは
建設業は、住宅や道路、橋梁など人々の生活に直結する社会基盤を築く重要な役割を担う産業です。そのため、建設工事の請負を業として行う場合(建設業)は、建設業法に基づき国土交通大臣または都道府県知事から許可を受けることが原則として義務付けられています(建設業法第3条第1項)。
しかし、例外として「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には許可は不要と定められています(同条第2項)。では軽微な建設工事とはどのような工事でしょうか。
法律上は次の範囲の工事を指します。
- 建築一式工事の場合:1件の請け負い代金が1,500万円未満、または請け負い代金にかかわらず延べ面積が150 m2未満の木造住宅の工事
- 建築一式工事以外の場合:1件の請け負い代金が500万円未満
上記のように建築一式工事であれば代金1,500万円未満(または木造住宅で延べ150 m2未満)、それ以外の工事であれば代金500万円未満であれば許可を取らずに施工できます。
なお、これら金額の算定には消費税を含む総額で判断する必要があります。また、仮に工事契約を分割しても合算して金額を算出する決まりであり、材料費や運送費等も含めて計上しなければなりません。工事を分割することで上限をくぐり抜けることはできない点に注意が必要です。
たとえば、小規模なリフォームで契約金額が500万円に満たないような工事であれば無許可でも可能ですが、500万円を超えるような工事を請け負うには許可が必要になるということになります。
建設業法3条(建設業の許可) 1 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。 一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの 2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。 建設業法施行令1条の2(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事) |
(出典:e-GOV法令検索『建設業法』)
建設業許可の種類
建設業の許可にはその請け負う工事の規模や立場に応じて「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります(建設業法第3条第6項)。「一般建設業許可」は、軽微な工事を超える建設工事全般を請け負うために必要となる基本的な許可です。元請け・下請けの別を問わず、原則として軽微な工事以上の建設工事を行う場合はこの一般許可を取得しなければなりません。
たとえば、下請け会社として工事を行うケースや、元請けでも下請け会社を使わず自社施工で完結するケース、あるいは元請けが下請けに出す工事金額が一件当たり4,500万円未満(建築一式工事なら7,000万円未満)で済むような場合は、一般建設業許可で対応可能です。
一方で、「特定建設業許可」は大規模な元請け工事を扱うための許可です。発注者(施主)から直接請け負った元請け会社が、一つの工事で下請け会社へ支払う合計金額が4,500万円以上に達する場合(建築一式工事の場合は7,000万円以上)には、一般許可ではなく特定建設業許可を取得する必要があります。
これは大規模工事において多数の下請け会社を適切に指導・統括できる体制や資力を備えた会社であることを担保するための制度です。特定建設業許可を取得するには、一般許可の場合よりも厳格な基準(経営経験や財産的基盤など)が課されており、主にゼネコンや大手工務店など大規模工事の元請けを担う企業がこの許可を取得します。
なお、特定建設業許可を持つ会社であっても、自ら下請けに出さずに施工する場合や下請けとして施工する場合は一般許可と同様に扱われます。逆に言えば、下請け会社であっても軽微な工事以上を請け負うなら一般許可は必要です(特定許可は元請け向けの制度なので下請けのみの会社は通常一般許可となります)。
建設業法3条(建設業の許可) 6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。 |
(出典:e-GOV法令検索『建設業法』)
無許可営業の罰則や処分
もし建設業許可を得ずに軽微な範囲を超える建設工事を営業すると、建設業法違反(無許可営業)となり厳しいペナルティーを受けるリスクがあります。具体的には、刑事罰として「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます(建設業法47条1項1号)。悪質な場合には懲役刑と罰金刑の両方が併科されることもあります。
さらに行政上の監督処分もあり、違反が発覚すると所管官庁から指示処分(業務改善命令)や営業停止処分、建設業許可の取り消し処分が科される恐れがあります。許可を持たずに違法な営業を行った結果、今後の許可取得も困難になるケースもあります。
実際に一度許可を取り消されてしまうと、その処分から5年間は新たな許可を受けられず、その間は軽微な建設工事しか行えなくなるため、事業継続が難しくなります。このように無許可営業は企業にとって致命的なダメージとなりかねません。
実際の摘発事例として、無許可で高額な工事を請け負った会社が逮捕されたケースも報告されています。たとえば2023年には、許可を受けずに約693万円の屋根修繕工事や530万円の外壁塗装工事を請け負った疑いで、リフォーム会社の関係者4名が建設業法違反容疑で逮捕されました。いずれも軽微な工事の範囲(500万円以下)を大きく超えており、無許可営業の悪質な違反として刑事事件にまで発展したものです。
このように違反が発覚すれば厳しい処罰を受けるため、無許可で建設業を営むことは極めてリスクが高いといえます。
建設業法に違反しないために
建設業法のルールを守るためには、まず許可制度に関する正確な知識を持つことが重要です。自社が請け負おうとする工事が「軽微な建設工事」に該当するのか、それとも許可が必要な規模なのかをしっかり確認しましょう。
特に500万円や1,500万円といった金額基準は厳密に適用されるため、見積もり段階から意識する必要があります。先述のとおり契約金額は分割しても合計で判断されますので、契約を小分けにすれば許可不要といった安易な考えは禁物です。
また「下請けだから許可はいらない」という誤解も散見されますが、下請けであっても軽微な工事の範囲を超える工事を請け負うなら自社で許可を取得しておかなければなりません。
許可が必要と判断した場合は、早めに許可取得の手続きに着手することが肝心です。建設業許可を取得するには、会社または個人事業主として一定の経営経験や資格・実務経験を持つ専任技術者の配置、財産的基盤(一定額以上の自己資本など)を有していること、法令順守の体制が整っていること等、複数の要件を満たす必要があります。
これらの要件をクリアしたうえで、必要書類を整えて都道府県知事(営業所が複数都道府県にまたがる場合は国土交通大臣)へ申請を行います。手続きには専門知識が求められるため、行政書士などの許可申請の専門家に相談することをおすすめします。行政書士は建設業許可の申請代行業務に精通しており、書類の作成から要件チェック、役所とのやり取りまでスムーズに進めてくれます。
許可取得にかかる時間を短縮し、要件漏れなどによる申請ミスを防ぐためにも、専門家のサポートは有益です。
●記事のおさらい
最後に、今回の内容をQ&Aで確認しておきましょう。
Q:建設業許可が必要な工事とはどのようなものですか?
A:建設業を営むには原則として建設業許可が必要ですが、「軽微な工事」に該当する場合は例外的に許可不要です。具体的には、建築一式工事で1,500万円未満または木造で延べ面積150m2未満、それ以外の工事で500万円未満の請負い工事が該当します。
Q:無許可で建設業を行った場合、どのような罰則がありますか?
A:無許可で建設業を営むと、建設業法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。悪質な場合は併科されることもあり、営業停止や許可取り消しといった行政処分の対象にもなります。
●関連コラムはこちら
≫ 【建築業界の基礎知識】建物構造の種類とその特徴について分かりやすく解説
≫ 建築構造におけるヤング係数(弾性係数)について分かりやすく解説
執筆者
弁護士法人コスモポリタン法律事務所
杉本 拓也(すぎもと たくや)
単なる法的助言を行う法律顧問ではなく、企業内弁護士としての経験を活かして、事業者様により深く関与して課題を解決する「法務コンサルタント」として事業者に寄り添う姿勢で支援しております。国際投融資案件を扱う株式会社国際協力銀行と、メットライフ生命保険株式会社の企業内弁護士の実績があり、企業内部の立場の経験も踏まえた助言を致します。






