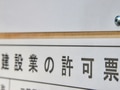工期ダンピングとは? 建設業法改正による規制や注意点について徹底解説

目次[非表示]
- 1.工期ダンピングとは
- 2.工期ダンピングの問題点
- 3.工期ダンピングの規制内容
- 4.建設会社の注意点
- 5.執筆者
工期ダンピングとは
工期ダンピングとは、建設工事を施工するために通常必要とされる期間よりも著しく短い工期を設定する請け負い契約を指します。
工期ダンピングが行われると、建設業に従事する労働者に長時間労働を強いることになり、手抜き工事の横行や事故発生のリスクも高まるため、近年その是正が強く求められてきました。
建設業界では労働環境の改善と安全確保が課題となっており、その観点から工期ダンピングを是正するための法規制が導入されました。
工期ダンピングの問題点
工期ダンピングによって生じる主な問題点は以下のとおりです。
(1)長時間労働の懸念: 通常必要な工期より大幅に短い期間しか与えられない場合、納期を守るために法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える長時間残業が常態化し、過労による事故や過労死のリスクが高まります。
(2)工事品質の低下: 工期に余裕がないと、工程の一部省略や手抜き工事が発生しやすくなります。必要な基礎工事や検査を省けば建築物の品質が損なわれ、重大な欠陥につながる恐れがあります。手抜き工事が発覚すれば建物の造り直しなどで結果的にコスト増・工期遅延を招きかねません。
(3)安全性の問題: 工期を無理に短縮すれば、現場で十分な安全対策を講じる時間的余裕もなくなります。疲労の蓄積や工程飛ばしにより労働災害や事故の発生率が高まるでしょう。
(4)業界の労働環境の悪化: 無理な工期設定が蔓延すると業界全体の労働環境も悪化します。多重下請け構造の下、下請け会社は「断れば次の仕事がもらえない」という不安から過酷な条件でも受注せざるを得ません。このような悪循環により業界全体の労働環境が悪化し、人材離れにもつながります。
工期ダンピングの規制内容
こうした問題を受けて、政府は2024年に関連法令を改正し工期ダンピング対策を強化しました。改正建設業法は2025年(令和7年)6月1日に施行予定であり、いわゆる「新・担い手三法」として建設業法、公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律(入契法)、公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)の3法が整備され、建設業における働き方改革と工期の適正化が図られています。
これらの改正は長時間労働の是正や人材確保といった建設業界の働き方改革の一環であり、2024年から建設業にも残業時間の上限規制が適用されており、もはや残業で無理な工期を埋め合わせることはできません。
主な改正内容は次のとおりです。
(1)建設業法の改正(著しく短い工期の禁止): 改正後の建設業法第19条の5により、発注者だけでなく受注者(請負人)も、通常必要な期間に比べ著しく短い工期の契約を結ぶことが禁止されました。従来は発注者側のみが規制対象でしたが、今回の改正で受注者による工期ダンピングも違法となり、現場労働者を酷使しない適切な工期設定が促されます。
(2)入札契約適正化法の改正(ダンピング防止): 改正入契法では、公共工事の入札・契約において、不当に低い価格や無理な条件での契約を防止する旨が基本方針に明記されました(入契法3条4号)。発注者は無理な安値発注や短工期の強要を行わないよう求められています。
(3)公共工事品質確保法の改正(適正な下請け契約の義務化): 改正品確法では、受注者の責務として下請け契約を締結する際に適正な請け負い代金と工期を定めることが義務付けられました(品確法8条2項)。元請け会社は下請け会社に対し、著しく不当な安値や短い工期で仕事を発注してはならないと法律で明確に規定されたことになります。
建設業法19条の5(著しく短い工期の禁止) 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律3条4号(公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項) (一~三 略) 公共工事の品質確保の促進に関する法律8条2項(受注者等の責務) |
(出典:e-GOV法令検索『建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律』)
建設会社の注意点
最後に、工期ダンピングに関する規制を踏まえ、建設会社が実務で注意すべきポイントを解説します。不当に短い工期で受注しないことはもちろん、適正な契約管理によって安全で持続可能な施工体制を築くことが重要です。
(1)適正価格での受注と工期見積もり: 受注段階で工事内容・規模に見合った適正な工期と費用を算出し、無理な短工期や安値で受注しない姿勢が大切です。過度な値引きや工期短縮のしわ寄せは現場の労働者や下請け企業に及び、品質や安全にも悪影響を及ぼします。
(2)契約変更協議の重要性: 工事の途中で設計変更や資材価格の高騰など予期せぬ事態が発生し工期や費用に影響する場合は、速やかに発注者と契約変更協議を行いましょう。改正建設業法では請け負い契約書に工期や代金の変更方法を定めることが義務化され、受注者から協議を申し出た際には発注者が誠実に応じる努力義務(公共工事では協議義務)を負うことになりました。契約内容を現場の実情に合わせて柔軟に見直すことで、無理を是正しトラブルを防止できます。
(3)元請け・下請け間の連携: 元請け企業は下請け会社と緊密に連携し、無理のない工程計画を現場全体で共有しましょう。自社が適正な工期で受注しても、下請けに無理な納期を課しては意味がありません。改正品確法の趣旨を踏まえ、下請け契約でも適正な工期・価格を設定し、定期的に進捗を確認して必要な調整を行うことで納期遵守と品質確保に努めることが重要です。
(4)違法な短工期の回避: 工期ダンピングが規制された現在、著しく短い工期での契約締結は発注者・受注者ともに禁止行為です。違反した場合は行政から是正勧告を受け、従わないと企業名公表などの措置を受ける恐れがあります。受注段階で工期が明らかに不十分と判断される場合は延長交渉を行い、それでも困難なら受注を見送る決断も必要です。適正な工期を守ることが労働者の安全と工事品質を守り、結果的に企業の信用維持にもつながります。
工期ダンピングの根絶と適正な工期確保は建設業界の持続的発展に不可欠です。改正法の趣旨を踏まえ、発注者・受注者双方が協力して健全な施工環境を整えることで、安全で高品質な建設工事と働きがいのある職場を実現していきましょう。
●記事のおさらい
最後に、今回の内容をQ&Aで確認しておきましょう。
Q:工期ダンピングとは何でしょうか?どのような問題があるのでしょうか?
A:工期ダンピングとは、建設工事において通常より著しく短い工期で契約を結ぶことを指します。これにより、長時間労働の常態化や手抜き工事のリスクが高まり、労働者の安全や建設物の品質に悪影響を及ぼします。業界全体の労働環境も悪化し、人材確保が困難になる恐れがあります。
Q: 工期ダンピングに対する規制と建設会社が注意すべき点は何でしょうか?
A:2025年施行の改正建設業法では、発注者・受注者ともに著しく短い工期の契約を結ぶことが禁止されました。入契法や品確法も連動し、適正な工期と価格の確保が義務付けられています。会社は適正な見積もりや契約変更協議を重視し、現場全体で無理のない工程管理を行うことが重要です。
●関連コラムはこちら
≫ 建築資材の価格高騰はいつまで続く? 高騰の理由と今後の見通し
≫ 国産木材活用住宅ラベルとは?表示制度の概要、メリットと表示方法を解説
執筆者
弁護士法人コスモポリタン法律事務所
杉本 拓也(すぎもと たくや)
単なる法的助言を行う法律顧問ではなく、企業内弁護士としての経験を活かして、事業者様により深く関与して課題を解決する「法務コンサルタント」として事業者に寄り添う姿勢で支援しております。国際投融資案件を扱う株式会社国際協力銀行と、メットライフ生命保険株式会社の企業内弁護士の実績があり、企業内部の立場の経験も踏まえた助言を致します。