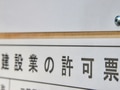建設業法違反となる取引とは? 注意点と対策方法について徹底解説!

目次[非表示]
建設業法の請け負い契約に関する規制の概要
建設業法違反は、建設工事の適正な施工を確保し発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を図ることを目的としています。そのため法律自体に、建設工事の請け負い契約を公正なものにするための規定を設けています(建設業法第3章)。
たとえば、建設業法18条(建設工事の請け負い契約の原則)では「建設工事の請け負い契約の当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない」と定められています。これは元請け・下請けの力関係にかかわらず、お互い公平で誠実な契約にしなければならないという基本原則です。
しかし、現実には契約内容が不明確だったり、一方に有利な条件で契約が結ばれてしまったりするケースも考えられます。それでは後日の紛争の原因にもなり、建設工事の適正な施工が妨げられるお恐れがあります。そこで建設業法は具体的に、契約書の作成や見積もり条件の提示、下請け代金の支払いなどについて詳細なルールを定め、契約の適正化を図っています。
加えて、国土交通省はこれらのルールを周知し違反を防止するために「建設業法令遵守ガイドライン」を策定しています。2024年12月には第11版が公表されました。ガイドラインでは元請け・下請け契約に関する留意点が具体的な事例とともに解説されており、元請け企業・下請け企業双方が法律の不知による違反をしないようにサポートする役割を果たしています。
以上が建設業法における請け負い契約規制の概要と、その趣旨(なぜ規制があるのか)およびガイドラインの存在意義です。具体的なルールについていくつか詳しく見ていきましょう。
見積もり条件の提示に関するルール
建設工事を元請け会社が下請け会社に発注する際、見積もり依頼時のルールとして「見積もり条件の提示」と「見積もり期間の確保」が定められています。建設業法20条では、発注者(元請け負い人)は契約締結までに下請け負い人に対しできる限り具体的な契約条件を提示しなければならず、併せて見積もり作成に必要な一定期間を設けなければならないと規定されています。
見積もり条件の提示とは、契約の重要事項を事前に具体的に示すことです。法律上は契約書面に記載すべき事項(後述する建設業法19条1項各号の内容)のうち主要なポイント15項目について、できるだけ明確に伝えるよう求められています。元請け会社はこれらをあらかじめ具体的に示し、下請け会社が条件を理解したうえで見積もりを作成できるようにしなければなりません。
見積もり期間の確保も重要なルールです。建設業法20条2項、同条4項、および建設業法施行令6条の規定により、下請け会社が見積もりを作成するための最低限の期間が工事規模に応じて定められています。具体的には以下のとおりです。
- 下請け工事の予定価格が 500万円未満 の場合:見積もり期間は中1日以上(最低2日間)
- 下請け工事の予定価格が 500万円以上〜5,000万円未満の場合:見積もり期間は中10日以上
- 下請け工事の予定価格が 5,000万円以上 の場合:見積もり期間は中15日以上
もし元請け会社がこれらの規定に反して、契約条件をあいまいにしたまま見積もりを出させたり、必要な見積もり期間を与えずに短期間で契約を結んでしまった場合、建設業法第20条違反となります。
実際の運用では、ガイドラインにも「見積もり条件を明示せず見積もりを行わせる行為」や「見積もり期間を必要より短く設定する行為」は違法とされる具体例として挙げられています。元請け・下請け間の健全な取引のためにも、見積もり依頼時には条件の明示と十分な期間の確保を徹底することが大切です。
建設業法20条(建設工事の見積り等) 2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。 3 建設業者は、前項の規定による見積書の交付に代えて、政令で定めるところにより、建設工事の注文者の承諾を得て、当該見積書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該建設業者は、当該見積書を交付したものとみなす。 4 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第十九条第一項第一号及び第三号から第十六号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。 |
(出典:e-GOV法令検索『建設業法』)
建設業法施行令6条(建設工事の見積期間) 一 工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上 2 略 |
(出典:e-GOV法令検索『建設業法施行令』)
書面による契約締結義務
建設業法では、建設工事の請け負い契約は必ず書面で取り交わすことが義務付けられています。建設業法19条1項は「建設工事の請け負い契約の当事者は、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならない」と規定しています。簡単に言えば、口約束だけで工事契約を済ませてはいけないということです。
実際、民法上は口頭の合意だけでも契約は成立しますが、それでは内容が不明確になり紛争のもとになりかねません。そこで建設業法が特別に契約書面の作成と交付を義務化しているのです。この規定はたとえ小規模な軽微工事(建設業許可が不要な規模)であっても適用されます。また「契約の当事者」には、発注者と元請け会社だけでなく元請けと下請けの契約関係も含まれるため、下請け契約でも同様に書面契約が必要となります。
具体的には、16項目にわたって記載すべき契約事項を列挙しています。
主な項目は以下のとおりです。
(1)工事内容(どんな工事を行うか)
(2)請け負い代金の額(工事代金の金額)
(3)工事着手の時期および完成の時期(いつ工事を開始し、いつ完成させるか)
(4)工事をしない日や時間帯の定め(休日や夜間作業の有無とその内容)
(5)前払い金・出来高払いの定め(あれば、その支払い時期と方法)
(6)設計変更・工期延期・中止の場合の取り決め(工期や代金の変更、損害負担等)
(7)天災など不可抗力の場合の取り決め(工期延長や損害負担等)
(8)物価変動による代金や工事内容の変更(価格変動が生じた場合の扱い)
(9)第三者への損害賠償の定め(工事により第三者に損害が出た場合の責任)
(10)発注者支給材・貸与機械の取扱い(発注者が提供する資材・機材がある場合の条件)
(11)完成後の検査方法と引き渡し時期(発注者による出来栄え検査の方法、引き渡し日程)
(12)完成後の代金支払い時期・方法(竣工後の支払い条件)
(13)契約不適合の担保責任(いわゆる瑕疵担保責任やそれに関する保証の取り決め)
(14)債務不履行の場合の損害金(工期遅延など契約違反時の遅延利息・違約金等)
(15)紛争の解決方法(仲裁や訴訟など、紛争が生じた場合の処理方法)
(16)その他国土交通省令で定める事項(上記以外で省令に定められた事項)
これらは建設工事の契約内容をめぐるトラブルを未然に防ぐための重要な事項です。特に工期や支払い条件、変更時の取り決めなどは工事遂行に直結するため、おろそかにできません。契約書の様式自体は自由ですが、上記のような必須事項が漏れていると建設業法違反となります。
また、書面の電子化に際しても記載事項を満たし、適切に電子署名を行えば建設業法上有効とされています(2022年の改正で押印義務が緩和され、電子契約も明確に認められました)。
建設業法違反となれば営業停止など厳しい処分につながりかねないので、どんな小さな工事でも必ず契約書を取り交わす必要があります。
下請け代金に関するルール
建設工事においては、元請け会社が下請け会社に対して適正に代金を支払うことが重要です。これに関して建設業法では、支払い期限と支払い方法について具体的なルールが定められています。
(1)支払い期限の原則と特定建設業者の追加義務
建設業法24条の3では、元請け会社が下請け会社に対して代金を支払う際、工事完成後できる限り早く、遅くとも1ヶ月以内に支払うことが義務付けられています。ここで注意すべきは、発注者(施主)からの入金状況にかかわらず、元請けは独立して支払い義務を負うという点です。
さらに、元請けが「特定建設業者」に該当する場合(原則として資本金が4,000万円以上で一定規模の工事を請け負う会社)、建設業法24条の6により、より厳格な規制が課されます。この場合、下請け会社が完成品を引き渡す申し出をした日から50日以内に支払い期限を設定する必要があります。
したがって、特定建設業者には「1ヶ月以内」または「50日以内」のいずれか早いほうの期限までに代金を支払う義務があることになります。
(2)支払い手段に関するルール
支払い方法についても、下請け会社の立場に配慮した規定があります。2020年の改正により、建設業法では「できる限り現金で支払うよう配慮すること」(24条の3第2項)と明記されました。ここでいう「現金」とは、銀行振り込みや当座預金による支払いなど、即時に現金化が可能な手段を含みます。
一方、手形払いを行う場合は特に注意が必要です。ガイドラインでは、割引困難な手形や長期サイトの手形を交付することは、下請け会社にとって不利益となるため、望ましくないとされています。一般的には、手形サイトは60日以内とすることが妥当とされ、それ以上の長期になると建設業法24条の6に違反する可能性があります。
また、手形による支払いの際には、手形割引料の負担についても、下請け側に過度な負担がかからないように配慮する必要があります。こうした点が軽視されると、元請けと下請けとの信頼関係を損なうだけでなく、法的リスクも伴います。
このように、下請け代金の支払いについては、元請け会社が一方的に支払い時期や手段を決めてよいものではなく、建設業法に基づいた明確なルールに従う必要があります。
|
建建設業法24条の3(下請代金の支払)
1 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。 2 前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
3 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
|
(出典:e-GOV法令検索『建設業法』)
|
建設業法24条の6:(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
1 特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、第二十四条の四第二項の申出の日(同項ただし書の場合にあつては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して五十日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。 2 特定建設業者が注文者となつた下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかつたときは第二十四条の四第二項の申出の日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは同条第二項の申出の日から起算して五十日を経過する日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
3 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。
4 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金を第一項の規定により定められた支払期日又は第二項の支払期日までに支払わなければならない。当該特定建設業者がその支払をしなかつたときは、当該特定建設業者は、下請負人に対して、第二十四条の四第二項の申出の日から起算して五十日を経過した日から当該下請代金の支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に国土交通省令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
|
(出典:e-GOV法令検索『建設業法』)
●記事のおさらい
最後に、今回の内容をQ&Aで確認しておきましょう。
Q:建設業法ではどのような請け負い契約上のルールが定められているの?
A:建設業法では、請け負い契約が公正かつ誠実に結ばれるよう、見積もり条件の提示、契約書の作成、代金支払いの方法と時期など、取引の各段階において具体的なルールが設けられています。国土交通省のガイドラインも整備されており、元請け・下請けいずれの立場でも遵守すべき基準が明確になっています。これにより、不当な取引条件やトラブルの発生を未然に防ぎ、健全な建設業の発展が図られています。
Q:違反を防ぐために元請け・下請けが気をつけるべきポイントは?
A:見積もり依頼の際は、契約条件を明確に提示し、下請け会社が十分な期間で見積もりを作成できるよう配慮する必要があります。また、契約書には法律で定められた項目をもれなく記載し、書面で交付することが義務です。さらに、工事完了後は代金を速やかに、原則1ヶ月以内に支払い、可能な限り現金での支払いを心がけましょう。こうした基本的なルールを守ることで、違法行為を防ぎ、信頼ある取引関係を築くことができます。
●関連コラムはこちら
≫ 建築基準法の道路斜線制限とは?適用距離や計算式、緩和条件を解説
≫ 偽装請負とは?判断基準と罰則・法的リスク、防止対策について解説!
執筆者
弁護士法人コスモポリタン法律事務所
杉本 拓也(すぎもと たくや)
単なる法的助言を行う法律顧問ではなく、企業内弁護士としての経験を活かして、事業者様により深く関与して課題を解決する「法務コンサルタント」として事業者に寄り添う姿勢で支援しております。国際投融資案件を扱う株式会社国際協力銀行と、メットライフ生命保険株式会社の企業内弁護士の実績があり、企業内部の立場の経験も踏まえた助言を致します。