建設業でも電子契約が可能に!電子契約に必要な条件とシステム導入時の注意点を徹底解説
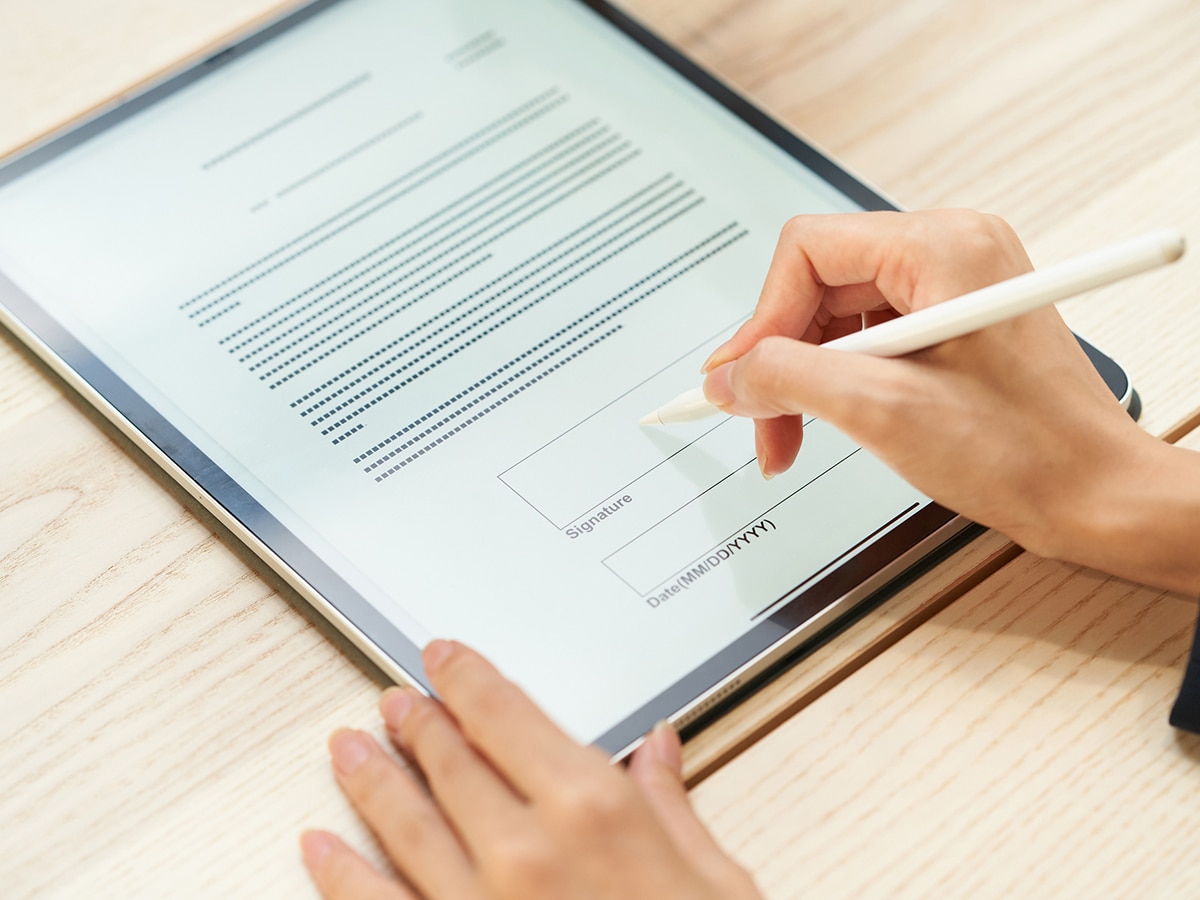
企業におけるペーパーレス化の流れが進むなかで、改めて注目を集めているのが「電子契約」の仕組みです。建設業においても電子契約は利用可能であり、きちんと導入すれば企業にさまざまなメリットをもたらします。
今回は建築業界における電子契約の流れや、電子契約を取り入れるメリット、電子契約システムを導入する際の注意点などについて詳しく見ていきましょう。
目次[非表示]
- 1.電子契約とは
- 2.建築業界でも電子契約は利用可能に!
- 2.1.建設業法の改正
- 2.2.グレーゾーン解消制度
- 3.建設業で電子契約を利用するメリット
- 3.1.業務効率化
- 3.2.コスト削減
- 3.3.コンプライアンス強化
- 4.電子契約に必要な条件3つとは
- 5.電子契約システム導入時の注意点
- 5.1.3つの要件を確認する
- 5.2.署名の方法を確認する
- 5.3.タイムスタンプ機能の有無を確認する
- 5.4.ほかのシステムとの連携のしやすさを確認する
電子契約とは
電子契約とは、契約締結をオンライン上で済ませる方法のことです。従来の契約方法では、契約書面に直接署名や捺印を行う必要があるため、対面や郵送によるものが当たり前とされてきました。
しかし、電子契約では電子ファイルに電子署名を行うことで、押印による契約と同様の法的効果が認められます。オンラインのみで手続きが完結し、契約にかかる時間やコストを削減できるのが大きな利点です。
特に新型コロナウイルスの蔓延により、非対面型でのサービスが普及していくなかで、電子契約に対する注目度も高まったといえます。コスト面でのメリットも大きいことから、今後もさまざまな企業で電子契約が導入されると考えられています。
なお、契約書という重要な書類を交わすため、電子契約は専門の電子契約システムを介して行われるのが一般的です。電子契約サービスを使えば、「管理画面に電子契約書をアップロードする」「受信側がメールで送付された電子契約を確認する」「端末上で電子署名を行い、契約を完了させる」というシンプルなステップで安全に手続きを済ませられます。
建築業界でも電子契約は利用可能に!
建築業界では法規制の影響や長年の商習慣などによって、その他の業界と比較しても電子契約の導入が遅れていた面があります。しかし、2001年の法改正によって、建設業の一部の契約においては電子契約が可能となりました。
建設業法の改正
建設業法は、建設業における基本的なルールとして1949年に施行された法律です。建設業法第19条では、工事請負契約を結ぶ際に「その内容書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」と定められており、工事請負契約書の書面化が義務付けられていました。
しかし2000年代に入り、IT革命が国を挙げて進められると、電子契約の流れが加速していきます。こうした流れを受け、2001(平成13)年4月に建設業法の一部が改正され、以下の項目が追加されたことで建設業界でも電子契約が利用できるようになりました。
■建設業法第19条第3項
建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。 |
※参照:建設業法
このように現行法では、建設業の工事請負契約においても「相手方の承諾を得る」「技術的基準に適合する」という2つの条件を満たすことで、電子契約が利用できるようになっています。
グレーゾーン解消制度
前述のように、法律の改正が行われたのは2001年であり、それほど新しい出来事ではありません。それにもかかわらず、建設業界ではあまり電子契約の流れが進んでいきませんでした。
その原因として考えられたのが、「技術的基準に適合する」という条件の複雑さです。どのような電子契約サービスが技術的基準を満たしているのかは、専門的な知識がなければ判断が難しく、実務での運用には高いハードルがありました。
その解消策として2018年に政府が設けたのが、「グレーゾーン解消制度」という制度です。グレーゾーン解消制度とは、経済産業省を通じて、電子契約システムなどの事業が法解釈と矛盾していないかどうかを照会できる仕組みです。
この制度で認められた電子契約システムを利用すれば、安心して電子で工事請負契約を結ぶことができます。
建設業で電子契約を利用するメリット
建設業で電子契約を利用するメリットには、大きく分けて3つのポイントがあります。
業務効率化
一つめのメリットは、契約業務の効率化が行える点です。電子契約であれば、インターネット環境さえ整っていればいつでもどこでも業務が行えるため、時間や場所にとらわれずに締結できます。
また、紙書類による契約で必要だった契約書の印刷や、収入印紙の貼付、郵送、返送後のファイリングなどを削減できるため、業務負担が大幅に軽減されます。
コスト削減
電子による契約では、収入印紙代や印刷コスト、郵送料といった経費を削減できるのもメリットです。特に建設業では印紙代が高額になりやすいため、費用を丸ごと削減できるのは大きな利点といえます。
また、書類を保管するコストや、関連業務で発生する人件費も節約可能です。
コンプライアンス強化
電子契約システムは、高度なセキュリティ性を備えているため、情報管理におけるコンプライアンスの強化にもつながります。電子契約書はアクセス権限を持つユーザーしか閲覧できないため、改ざんや不正といったトラブルを防止できます。
電子契約に必要な条件3つとは
建設業法施行規則では、建設業で電子契約を行う際の要件として、「見読性」「原本性」「本人性」の3つが定められています。これらは、いずれも契約上の安全確保や紛争防止のために重要な項目です。
ここでは、それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
見読性
見読性とは、契約の相手方がデータを取り出し、書面などの形式でも表示できることが可能である状態を指します。電子契約を結ぶ際には、単にクラウド上で電子データを保管するだけでなく、必要があればディスプレイや書面で閲覧・出力できるようにしなければなりません。
また、電子データの特性を生かし、記録がいつでもスムーズに取り出せるように適切な検索機能を備えておくことが望ましいとされています。
原本性
原本性とは、契約書が改ざんされていないかどうかを客観的に確認できる状態を指します。電子契約書は内容が改変されていてもその痕跡が残らないという問題があるため、特に契約期間が長期にわたりやすい建設工事の請負契約では、原本性の確保も重要なポイントです。
具体的には「公開鍵暗号方式」による電子署名などを用いて、改ざんされていないことの証明を行えるようにしておくといった方法があります。
本人性
本人性は、2020年に行われた建設業法施行規則の見直しにより、新たに加えられた要件です。本人性とは、契約の相手方が本人であることを確認できる状態を意味します。
この点については、第三者として電子契約システムの事業者が電子署名を行う「立会人型電子契約」でも十分である旨が、国土交通省によって明らかにされています。
電子契約システム導入時の注意点
電子契約システムはさまざまな事業者によって取り扱われています。どのシステムを利用するかは、そのシステムの安全性や自社との相性を踏まえて慎重に検討することが大切です。
ここでは、電子契約システムを選定する際の注意点をご紹介します。
3つの要件を確認する
まずは、導入を検討している電子契約システムが「見読性」「原本性」「本人性」の3つの要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。見読性については、契約内容やディスプレイや書面でも明瞭に表示されるかどうかをチェックしましょう。
原本性や本人性については、公開鍵暗号方式による電子署名が用いられているか、立会人型電子契約が行えるかなどを確認することが大切です。
署名の方法を確認する
電子契約システムのなかには、署名の方法に電子サインを用いるタイプと電子署名を用いるタイプがあります。電子サインとはタブレットなどのデバイスにタッチペンなどで書き込む署名も含んだ方法であり、暗号化されていないため、偽造や改ざんのリスクがあるのがデメリットです。
電子署名はきちんと電子署名法に準拠した署名方法であるため、安全性を考慮するうえではこちらを用いたシステムを選ぶほうがよいでしょう。
タイムスタンプ機能の有無を確認する
タイムスタンプとは、インターネット上の取引や手続きが行われたときに、その時刻に電子文書が確かに存在していたことや、その時刻以降に修正や改ざんが行われていないことを証明する技術のことです。現状の法制度で言えば、電子契約を結ぶ際に必ずしもタイムスタンプがなければ成立しないというわけではありません。
しかし、タイムスタンプがあれば電子契約の完全性が保たれるとともに、「電子帳簿保存法への対応が容易になる」「電子署名の長期保存ができる」「不正なバックデートを避ける」といったメリットが生まれます。そのため、システムの選定時には、タイムスタンプ機能があるものを選ぶほうが望ましいといえます。
ほかのシステムとの連携のしやすさを確認する
電子契約システムを選ぶ際には、その他のシステムとの連携しやすさにも目を向けることが大切です。自社で利用している基幹業務システムや管理システムなどと連携できるものであれば、現場での混乱を避けてスムーズに導入しやすくなります。
●記事のおさらい
最後に、今回の内容をQ&Aで確認しておきましょう。
Q:電子契約とは?
A:電子契約とは、電子契約システムを用いて、オンライン上で契約を締結する方法のことです。オンラインのみで手続きが完結するため、契約にかかる時間やコストを削減できるのが大きな利点です。
Q:建設業で電子契約は行える?
A:2001年の建設業法改正により、建設業でも一部契約において電子契約が可能となっています。ただし、建設業で電子契約を用いる際には、「相手方の承諾を得る」「技術的基準に適合する」という2つの条件を満たす必要があります。
Q:建設業の電子契約を行う要件とは?
A:建設業法施行規則では、電子契約を行う要件として「見読性」「原本性」「本人性」の3つが定められています。電子契約を行う際には、これらの要件を満たしたシステムを用いる必要があります。
●関連コラムはこちら






